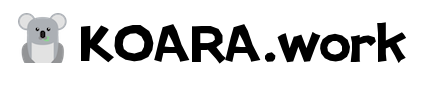2025/06/22

未来予測系の本は、その内容もそうだがそれ自体がきっかけとなって、未来のことをあれこれと思考を巡らすことに繋がるのが面白い。
また、世界情勢がどうなっているのか、というのは常に自分は未学の段階で、知らないことに溢れている。
政治、テクノロジー、人口動態、経済状況、幸福度あたりがメインで語られている本であり、他の未来予測系もその辺がテーマとなっていることが多いが、この本もそうで、書いてあることについて、あらかじめ知っていたことはあまりなく、ビジネス書などは「だよな!」と思うことも多くあるが、これらの本は「そうなんだ!」となる瞬間こそに価値がある。
ファクトフルネスという本が売れていたが、その内容にも通ずる、「世界は言うほど悪くなっていない」と一節にまとめられるところから抜粋。
未来について考えるのは、悲観になるためでもないし、世界が悪くなっていると言う方向で考えていく方が、プロスペクト理論(人間は損失を回避する方に比重を置く)にも通ずる形で響きやすい。でも、実際には世界全体では豊かになってきていると言うのが概ねの正しい実数値で、部分的にはそうでないにせよ、あまりにも悲観に偏るのは、そもそも楽しくない。
過去の人たちが目指してきた未来の輝きは、達成されていることが多い。そこにありがたみを感じることがまず先なのではないかと考える。そういうきっかけが手に入る本。
物事は悪くなっていると言えば、思慮深い人に見られる。物事はよくなっていると言えば、世間知らずと呼ばれるのはまだいい方で、馬鹿呼ばわりされる時もある。ピンカーによると、人類はこれからも進歩すると解く楽観的な本はたくさん出版されているが、主要な賞をとったものは一つもない。
これに対し、ノンフィクション部門のピューリツァー賞は「ジェノサイドに関する本4冊、テロリズムに関する本3冊、がんに関する本の2冊、レイシズムに関する本2冊、絶滅に関する本1冊」に与えられている。しかし、間違っているのは大抵悲観論であり(少なくとも全体として)正しいのは楽観論の本である。